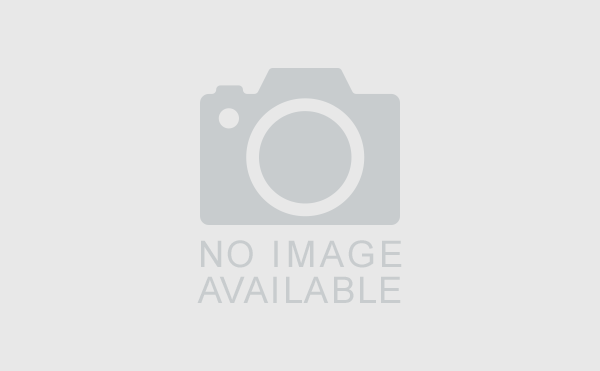日本と台湾の労働法の違いとは?就業規則・賃金・労働時間など
アジアでも経済的に密接な関係を持つ日本と台湾。両国とも労働者保護の視点から整備された労働法制を有していますが、実務レベルでは意外な共通点も多く存在します。本記事では、就業規則、労働条件など主要テーマごとに比較し、日台でビジネスを行う上で注意すべきポイントをまとめました。
※下記の情報は、すべて2025年7月現在のものです。
1. 日本も台湾も「労働基準法」
まず、日本と台湾の両国ともに「労働基準法」が基本となる労働関係の法律として位置づけられています。労働時間、賃金、休暇など労働条件の最低基準を定める役割を果たしており、この点では両国に大きな違いはありません。
2. 就業規則の作成義務
台湾:事業所単位で労働者が30人以上で工作規則(日本でいう就業規則)の作成が義務。
日本:事業所単位で労働者が10人以上で作成義務が発生。労基署への届出が必要。
3. 最低賃金制度
台湾:全国一律(月額28,590TWD)。物価の地域差を考慮しないシンプル設計。
日本:都道府県ごとに設定(東京都:時給1,163円など)。地域差を反映した制度。
4. 休憩時間
台湾:4時間勤務ごとに30分以上の休憩。
日本:6時間超で45分、8時間超で1時間の休憩。
5. 時間外労働と割増賃金:台湾の方がやや高め
台湾:通常日で2時間以内は1.33倍、それ以降1.66倍/休日2.33倍など。
日本:1.25倍(時間外)など。
両国の労働法は多くの共通点を持ちながらも、用語や運用の違いがあるため、現地での法令遵守を図るには正確な知識と対応が求められます。とくに「就業規則」や「労働契約書」を整備する場合、単なる翻訳ではなく、各国の法制度に即した内容である必要があります。